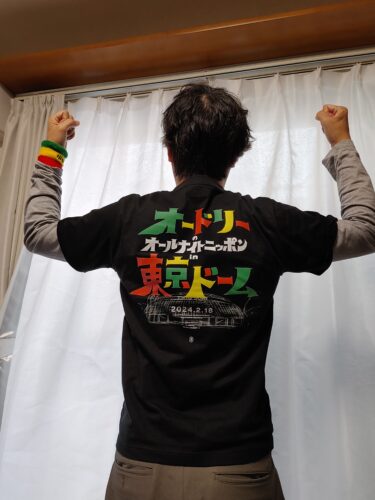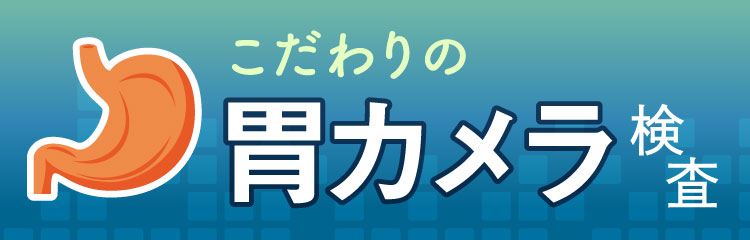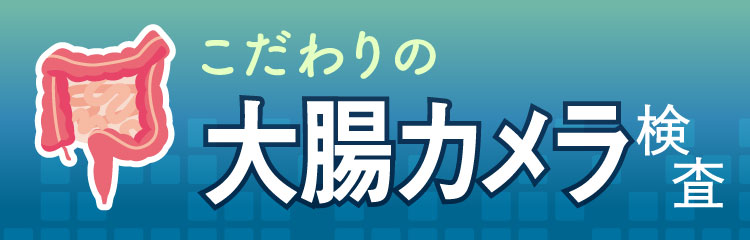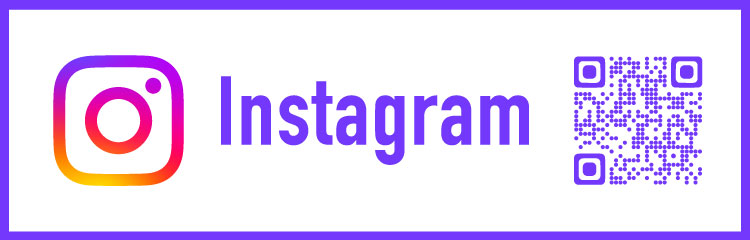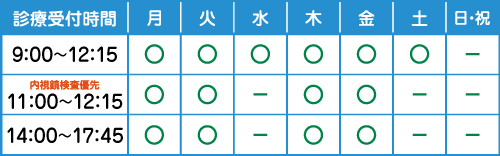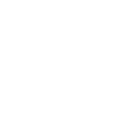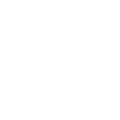福岡市博多区の大腸カメラ「あべ胃腸内視鏡・内科」
🐰たくさん稼いでも幸せになるとは限らない🐢
あるデーターによれば、年収800万(共働き世帯は1500万)以上は稼いでも幸せ満足度は上がらない、と言われているそうです。
ただ稼ぐことだけに囚われていたら、ただ好きでもない仕事に追われて無理をして体を壊したり、ノイローゼになったり…
資産はあるけど、幸せ度、満足度がひくいという事態になる可能性もあります。
【吾唯足知:われただたるをしる】
足るを知る者は地べたに寝るような生活であっても幸せを実感できるが、足るを知らないものは天にある宮殿のようなところに住んでいても満足できない。足るをことを知らないものはいくら裕福であっても心は貧しい、という教えです。
もし今、お金がないと困っている人は、一度悩みをスパッと切り裂いて一旦忘れてみてください。
自分が今すでにもっているものを数えてみてください。
家族、両親、子供、仲間、職場、仕事、趣味、自分の今まで積み上げた知識や経験…
意外と自分が恵まれていることに気づくと思います。まあまあ幸せだと。
本当は世の中は明るい貧乏が支えている…かもしれないです(#^^#)

🌸一笑すれば千山青(いっしょうすればせんざんあおし)🌸
人生、生きていればいろいろありますよね(>_<)
仕事のこと、人間関係のこと、家族のこと、子供のこと、老後のこと、病気のこと…
いつも心穏やかに過ごしたいだけなのに、突然起こる青天霹靂の出来事😱😢
よく、「自分の人生に悔いなし」とご年配の方から伺ったりしますが、私たちは悔いは大有り(笑)です。
日々、落ち込んだり、くよくよ考えたり…
最近、「自分を受け入れるスヌーピー」という本を買いましたが、心がほっとした一文がありましたのでご紹介します。
≪困難は「ハハハ!」と大きく笑い飛ばして切り抜ける≫
目の前のモヤモヤを(あっはっは)と笑い飛ばせば、青々とした山が見えてくる感じがしてきます。
2度と味わいたくないほどに、辛いことや身に染みて苦しいこと、そんな苦い経験を引きずる道を選ぶのでなく、
困難に遭遇してもくよくよ悩まず、笑い飛ばせば道が開けてきます。
今、どちらに進むべきか、右か左か真っ直ぐか迷うとき、全体を俯瞰して細かいことにとらわれずに一笑する。
その何とかなるさ、と笑う余裕が現状を打破します。
辛いこと、苦しいことも遭遇することもあるでしょう。でもそれも、全部自分の人生の財産。
全部、ひっくるめて生きていきましょう(⌒∇⌒)
こんにちは! あべ胃腸内視鏡内科・看護師の阿部です。
今季(2024年4月~2025年3月分)の胃がん検診のご案内です。
50歳以上の偶数年齢の方を対象に実施している胃カメラの検診です。
前季(2023年4月~2024年3月分)の受付は終了致しました。現在今季分の受付を開始しております。
対象者様
☆福岡市民の方(健康保険に関係なく、職場などで受診機会のない方)
☆令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に偶数年齢になる50歳以上の人(50.52.54.~)
🎂今年度内に対象年齢になる人は誕生日前でも検査できます!
☆料金:自己負担金1800円(通常の保険胃カメラの場合、5000~6000円かかりますのでかなりお得☺)
毎年、1月~3月の年度末は混みあいますので早めの検査がお勧めです。
尚、胃の不調のある方、自覚症状のある方は胃がん検診の対象になりません。通常の受診をおすすめします。
🌸がん検診でがんを早期に発見し、治療することにより、がんによる死亡リスクを減らすことができます。🌸
早期に発見できれば、身体への負担の少ない治療が可能です。
あなたとあなたの大切な人の為にも、検診を受けましょう👨👩👦👦